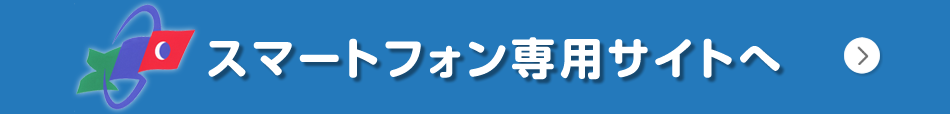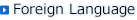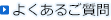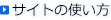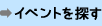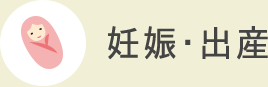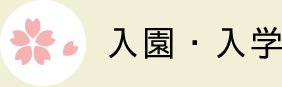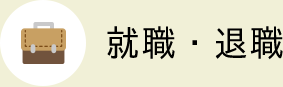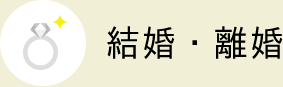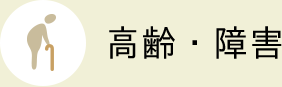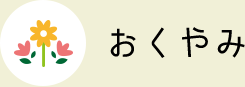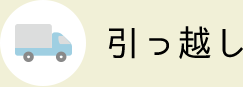給食センターの1日
作業開始

朝7時45分から作業を開始します。
マスクをつけ、髪の毛が出ないようネット・帽子をかぶり、身支度を整えます。
粘着テープで白衣の毛髪やほこりを取り除きます。

石鹸をよく泡立てて、個人用の爪ブラシを使い、手のひら、手の甲、爪や指の間、ひじまで丁寧に時間をかけて洗います。
ペーパータオルで水分を拭きとった後、アルコールで消毒します。
手洗い場は、調理場内の各所に設けており、作業途中・作業区分ごとに手を洗います。
納品・検収

食材が届いたら、数量・生産地・品質・鮮度・品温・異物の混入・賞味期限等について十分に点検を行い、納品します。
写真は地元農家から大根が納品されたところです。

2,000人分の給食を作るために、じゃがいも約190キロ、玉ねぎ約130キロ等毎日大量の食材を使用します。
野菜の下処理

検収室で、納品された食材の土を落としたり、皮をむいたりします。

土を落としたり、皮をむいた食材を、野菜下処理室のシンクで、3段階にわけて流水で丁寧に洗います。
虫や土がついていないか、異物が混入していないかを慎重に確認しています。
肉・魚・卵の下処理

肉・魚下処理室では、納品した肉や魚に下味をつけます。

多いときには、約2,000個の卵を1つ1つ割ります。殻が入らないように、割った卵を器に入れて確認し、ザルでこします。
野菜の切裁

スライサーで野菜を切ります。献立に合わせて、様々な形やサイズの幅に切ることができます。大量の野菜を短時間でカットできるとても便利な機械です。

スライサーで切ることができない野菜や、煮くずれてほしくない野菜は、調理員が包丁で切ります。
焼き物の調理

スチームコンベクションオーブンで焼きます。
蒸し焼きにできるので、食材がパサつかず、旨みを残したまま仕上げることができます。

焼き上がったオムレツです。
人数分に包丁で切り分けていきます。

焼き上がった魚です。

ケーキを焼くこともできます。
揚げ物の調理

連続式揚物機で揚げます。
その日の食材に合わせて、時間と温度を設定します。
ベルトコンベアーで流すので、効率的に作業を進めることができます。
たっぷりの油で揚げるので、カラリと揚げることができます。

揚げたときに、中まできちんと火が通っているのか確認するために、温度計を使って、中心の温度を測ります。
蒸気回転釜での調理

蒸気回転釜では、汁物・煮物等を調理します。
1釜で約700人分を作ります。
献立に合わせ、煮えにくい食材から順に入れて、煮込んでいきます。

煮込んだら、温度(85度以上を確保)と出来上がり量を確認します。
和え物の調理

細菌やウイルスによる食中毒を防止するため、和え物に使用する野菜も加熱し、中心温度が85度以上あることを確認します。

茹でた野菜を真空冷却機に入れ、約10分で、10度以下に冷やします。

冷やした食材は、和え物室でドレッシング等を入れて混ぜ合わせます。
保存食の採取

出来上がったすべての料理の、保存食をとります。
調理する前の材料も、保存食として保管しています。
原材料・調理済食品ともマイナス20度以下の冷凍庫で2週間保管します。
配缶

出来上がった給食を各クラスの食缶に配缶します。
クラスの人数や学年に合わせて、量の調整をします。
配送

出来上がった給食を、運搬用コンテナに入れます。

食缶や食器の入った運搬用コンテナを、配送車へ積み込みます。

2台の配送車で、給食を各学校に運びます。
配送車には、大竹市の食育キャラクターが描かれています。
洗浄
学校から戻ってきた食器・トレー・食缶・コンテナをそれぞれ専用の機械で洗浄します。

食器の洗浄

食缶の洗浄

食缶は残ったものを計量し、記録した後に洗浄します。
職員にとって、給食を残さず食べていただくことが何よりうれしいことです。
残菜量は、今後の献立・調理の参考にします。

洗浄機で洗った食器やトレーの数を数えて、各クラスごとにカゴに入れます。
消毒

食器具、食缶を消毒保管庫に入れて、90度の温度で、90分間熱風消毒します。

食器は、洗ったコンテナに入れ、コンテナごと熱風で消毒します。 以上が給食センターの1日の流れです。
毎日、安心安全でおいしい給食を届けるために、みんなで頑張っています。
更新日:2022年09月30日