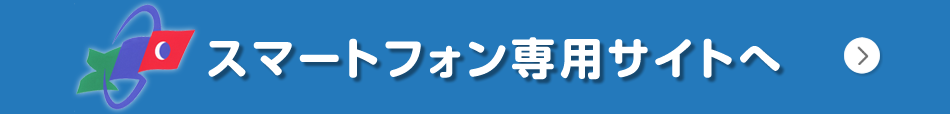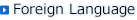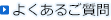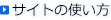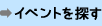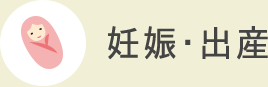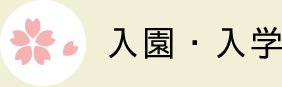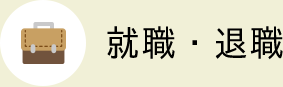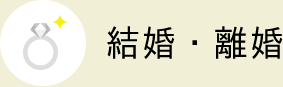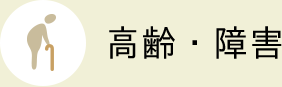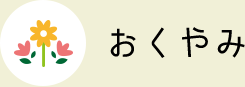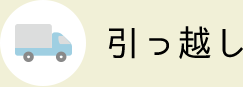高額療養費について
高額療養費とは
1か月(同じ月内)に医療機関などで支払う一部負担金(窓口負担金)が高額になったときは、一部負担金の合計額から次の表の自己限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。
また、マイナ保険証で医療機関を受診する際に高額医療費制度の利用に同意すれば、同一病院等ごとの1か月の窓口負担が、自己負担限度額までで済みます。
| 区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
| 外来 (個人ごと) | 外来+入院 (世帯単位(注意6)) | ||
| 市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者3(注意1) |
252,600円+(医療費‐842,000円)×1% |
|
| 現役並み所得者2(注意1) | 167,400円+(医療費‐558,000円)×1% (93,000円(注意5)) |
||
| 現役並み所得者1(注意1) |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1% |
||
| 一般2(注意2) | 18,000円または(令和7年9月30日までは、6,000円+医療費―30,000円×10%)の低い方を適用 | 57,600円 (44,400円(注意5)) |
|
| 一般1(注意3) | 18,000円 | 57,600円 (44,400円(注意5)) |
|
| 市町村民税非課税世帯 | 低所得者2 (注意4) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 (注意4) | 15,000円 | ||
(注意1)負担区分が3割の方です。現役並み所得者の区分については、現役並み所得1は課税所得が145万円以上380万円未満、現役並み所得2は課税所得が380万円以上690万円未満、現役並み所得3は課税所得が690万円以上となります。
(注意2)負担割合が2割の方で、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上の方です。
(注意3)負担区分が1割で、市町村民税世帯の方です。
(注意4)負担区分が1割で、区分については低所得者1は同一世帯全員が市町村民税非課税で背板に各種所得合計額が0円の方(公的年金控除額806,700円で計算)で、低所得者2は同一世帯全員が市町村民税非課税世帯で低所得者1に該当しない方です。
(注意5)()内の金額は、多数該当(療養を受けた月以前の12か月以内)に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当するときの金額です。
(注意6) 世帯員の加入している医療保険が異なる場合は合算できません。
高額療養費の申請手続き
支給の対象となる方には、診療した月から3~4か月後に広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入の上、国保年金係または支所にご申請ください。 一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。高額療養費の支給があれば、広域連合から、支給金額、振込日をお知らせします。
申請に必要なもの
- 支給申請の案内通知
- 支給申請書(申請案内に同封されているもの)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳など)
- マイナンバーカードなどのご本人が確認できる書類
入院時の食費と居住費
入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
市町村民税非課税世帯(低所得者1・2の区分)の方は、限度区分が併記された資格確認書を提示するか、マイナ保険証で受診することで、食費・居住費が対象の区分の額となります。
|
一般病床入院時の食事の負担額(表1) |
||
|---|---|---|
|
区分 |
食費(1食あたり) |
|
|
市町村民税課税世帯 |
510円 |
|
|
市町村民税非課税世帯 |
低所得者2 |
240円 |
|
低所得者2(長期入院該当者) |
190円 |
|
|
低所得者1 |
110円 |
|
|
療養病床入院時の食費・居住費の負担額(表2) |
|||
|---|---|---|---|
|
区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|
|
市町村民税課税世帯 |
510円(注) |
370円 |
|
|
市町村民税非課税世帯 |
低所得者2 |
240円 |
370円 |
|
低所得者1 |
140円 |
370円 |
|
療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされ、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
(注意)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、470円になります。
|
市町村民税非課税世帯の区分(表3) |
|
|
低所得者2 |
同一世帯の世帯全員が市町村民税非課税 |
|
低所得者2 (長期入院該当) |
低所得2に該当し、過去12か月の間の入院日数(低所得2に該当している期間に限る)が91日以上ある方 (91日目から申請が可能です) |
|
低所得者1 |
同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって、その世帯の各所得(公的年金所得は控除額を806,700円として計算)の合計額が0円となる方 |
(注意)負担区分が併記された資格確認書やマイナ保険証を提示し忘れた場合には市町村民税課税世帯の額が自己負担となります。その場合、食費・居住費の差額の支給はできません。
限度額適用認定を受けるには申請が必要です
資格確認書に限度区分の併記がない方で、現役並み所得者1・2に該当する方、または市町村民税非課税世帯(低所得者1・2の区分)の方は、申請が必要です。
その他の区分の方およびマイナ保険証を持っている方は、申請の必要はありません。
資格確認書併記の申請に必要なもの
- 資格確認書
- マイナンバーカードなど本人確認ができる書類
長期入院該当の方はご申請ください
長期入院該当の区分は、マイナ保険証等をお持ちの方であっても、認定を受けないと適用されません。
低所得者2の方で長期入院該当する場合(低所得2に該当する期間の過去12か月間に入院日数が91日以上ある方)は、国保年金係に申請してください。
低所得者2の方が長期入院該当の申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書(マイナ保険証の場合は「マイナポータルの資格情報画面の写し」を提出してください。
- 病院等が発行する入院期間がわかるもの(入院証明書、領収書など)
- マイナンバーカードなどのご本人が確認できる書類
更新日:2025年03月24日