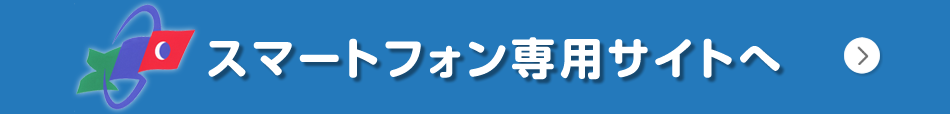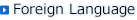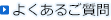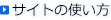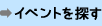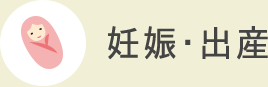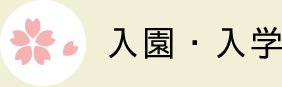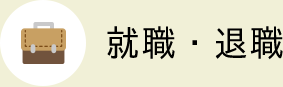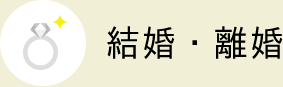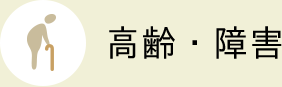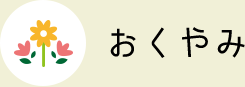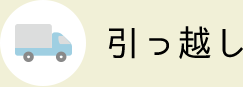下水道事業のあらまし
1.下水道の役割としくみ
下水道の役割
(1) 周辺環境の改善
人間の生活や生産活動に伴って生ずる汚水を速やかに排除し、住宅地周辺に停滞する蚊やハエ・悪臭の発生源を断つことにより、周辺環境が改善されます。
(2) 水質の保全
汚水や生活雑排水を処理した後、公共用水域に戻すので、水質汚濁を防ぎ、きれいな川や海の豊かな自然環境が改善されます。
(3) トイレの水洗化
下水道が整備されるとトイレの水洗化が可能となり、し尿は他の汚水とともに処理されるので悪臭のない快適な生活ができるようになります。
(4) 雨水の排除(浸水の防除)
下水道は河川、水路と共に雨水排除の機能を有し、大雨や洪水による浸水被害を防止する役目も担っています。
(5) 処理水の再利用
下水処理水は、水需給のひっ迫する都市域において、水洗トイレの雑用水等として利用される貴重な水資源となっています。
(6) 下水汚泥の有効利用
下水処理に伴って発生する汚泥は、資源制約の時代背景からコンポスト化による緑農地への施肥や燃料化されて再資源化されています。
(7) 下水道施設の有効利用
過密化した大都市においては、貴重なオープンスペースとして、下水道施設の上部に、公園、テニスコート、図書館などが設置されてきています。
下水道のしくみ

下水道は、下水を集めて処理場へ運ぶ管渠及びポンプ場、集められた下水を処理する終末処理場から構成されています。
家庭、工場、事業所から排水される汚水は、各家庭や工場に設けられた排水設備から汚水ますに流れ込み、下水管を通じて処理場へ流入し、清浄な水に処理された後、河川などへ放流されます。また、市街地に降る雨水は、雨水管を通じて直接河川などへ放流されます。
下水道の施設
下水道の施設には、次のようなものがあります。
(1) 排水設備
公共下水道に汚水を流すために、各家庭の敷地内に設置していただく、管やますなどの設備で、公共汚水ますへ接続します。排水設備は下水道を使用される方で設置管理をしていただきます。
(2) 下水道管
汚水を流すための円形の管であり、直径が150ミリメートルから流量によって大きくなります。また、管の途中には、維持管理のためのマンホールを設置します。このマンホールには、地形的に自然流下では管が深くなる場合、マンホール内のポンプで汲み上げ、管の埋設深さを浅くするマンホールポンプがあります。下水を運ぶ方式には、汚水と雨水をいっしょに運ぶ合流式と、それぞれ別の管で運ぶ分流式があります。大竹市は分流式(一部合流式)です。
(3) ポンプ場
下水道(汚水)は、自然流下を原則としており、下水道管を埋設する場合、適当な地形勾配がなく、河川横断など障害があると著しく深くなります。このような場合は、下水道管の途中にポンプ場を設け、いったん汚水を地表近くまで汲み上げます。なお、大竹市内に、公共下水道の汚水ポンプ場は5ケ所設置されています。
(4) 終末処理場
終末処理場では、流入してきた汚水を微生物などの作用を利用した生物処理方式によってきれいにします。終末処理場は、汚水を処理する水処理施設と、そこから発生する汚泥を処理する施設に分けられます。東栄三丁目の大竹下水処理場が水処理の終末処理場になります。

2.大竹市の公共下水道
(1)公共下水道事業の概要
大竹市は広島都市圏の最西部に位置し、小瀬川(一級河川)をはさんで山口県岩国市並びに和木町に接し、沿岸部一帯には石油コンビナート・紙パルプ・化学繊維などの企業が立地し、瀬戸内海工業地帯の一拠点として発展してきました。
しかし、急速な都市化及び産業経済の発展に伴う都市排水の増大は、生活環境の破壊と公共用水域の水質汚濁をもたらし、市民の保健衛生上極めて憂慮される状況になりました。 このため本市では、地方の小都市の公共下水道としては比較的早く、昭和35年11月に事業認可を受け、事業に着手しています。当初は合流式で314ヘクタール整備していましたが、約10年間で家屋の浸水多発地区の解消が図られたこと、また公共水域の汚濁防止を早急に図る必要から、昭和47年5月に排除方式を合流式から分流式に変更しています(下水道法事業認可変更)。
下水処理は、昭和43年に隣接する和木町との間に「下水終末処理事務の委託に関する規約」を締結し、第2次事業計画変更認可により汚水処理を行うこととなりました。昭和45年12月1日から簡易処理を開始し、さらに昭和48年12月1日に現在の高級処理施設(大竹下水処理場)が完成し、汚水処理(標準活性汚泥法)を開始しました。
現在は第14次認可計画で、認可面積は720.1ヘクタール、計画人口は25,600人です。平成25年度末までの整備済の状況を見ると、処理区域は673.6ヘクタール、処理区域内の人口は26,637人、そのうち下水道が接続された水洗便所設置人口は26,537人となっており、下水道人口普及率は94.0%です。
また、管渠については昭和36年度から布設工事を開始しており、平成28年度末までに約154.0キロメートルを整備しています。
(2)大竹市の下水道のあゆみ
昭和35(1960)年11月
公共下水道事業認可
昭和45(1970)年12月
下水道終末処理場(簡易処理)の完成と供用開始
昭和48(1973)年6月
下水道終末処理場広域処理開始
昭和61(1986)年3月
小方ポンプ場新設(建築)工事完成 大竹下水処理場管理棟新築工事完成
平成8(1996)年3月
漁業集落排水処理施設(阿多田地区)完成
平成10(1998)年3月
農業集落排水処理施設(栗谷地区)完成
平成18(2006)年4月
水道局と下水道課を統合し「上下水道局」が発足
(3)第17次変更認可計画と整備の現況
|
下水道当初事業認可 |
昭和35年11月4日 |
|---|---|
|
第17次変更認可 |
令和5年1月11日 |
|
事業認可面積 |
720.1ヘクタール |
|
計画人口 |
24,080人 |
|
計画処理水量 |
13,310立方メートル/日 |
(4)事業計画と整備の進捗状況
| 認可計画 |
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
進捗率 |
|---|---|---|---|---|
|
処理面積(720.1ヘクタール) |
703.9 | 703.9 | 703.9 | 97.8% |
|
処理人口(25,600人) |
26,470 | 26,249 | 26,057 | 101.8% |
|
ポンプ場(5ケ所) |
5 | 5 | 5 | 100.0% |
(5)今後の重点整備項目
普及促進
管渠の面整備については完了しましたが、引き続き普及促進に努めます。
汚水処理
処理場及びポンプ場においては、機械・電気設備の改築更新を順次行う予定です。
合流改善
平成17年度から、合流改善として、晴天時の不明水対策整備を行っています。
(6)汚水計画図と下水道施設の概要

| 施設の区分 |
名称(施設概要) |
所在地 |
|---|---|---|
|
終末処理場 |
大竹下水処理場 (施設概要) 敷地面積:2.83ヘクタール 処理方式:標準活性汚泥法 放流先:小瀬川 |
大竹市東栄三丁目 |
|
ポンプ場(汚水) |
小島汚水中継ポンプ場(合流) 小島汚水中継ポンプ場(分流) 小方ポンプ場(汚水ポンプ場) 玖波第一汚水中継ポンプ場 玖波第二汚水中継ポンプ場 |
大竹市東栄一丁目 大竹市東栄一丁目 大竹市小方一丁目 大竹市黒川一丁目 大竹市玖波一丁目 |
3.農業集落排水事業・漁業集落環境整備事業
(1)農業集落排水事業
本市の農業集落排水事業は、平成6年6月23日に農林水産省中国四国農政局長より事業承認を受け、平成6年度に、処理場の基本設計と管路の実施設計業務を実施しました。平成7年度より本工事に着手し、平成11年3月に完了をしました。平成10年6月に大栗林・小栗林を、また平成11年6月 に後原地区を供用開始しました。
| 事業名 |
農業集落排水事業(農林水産省補助事業) |
|---|---|
|
事業年度 |
平成4年度〜平成10年度 |
|
総事業費 |
1,122,000千円 |
|
全体計画面積 |
13.7ヘクタール |
|
処理区域面積 |
13.7ヘクタール(平成29年3月31日現在) |
|
全体計画人口 |
710人 |
|
計画処理能力 |
日平均:192立方メートル |
|
施設概要 |
栗谷浄化センター 所在地:大竹市栗谷町大栗林字曽根288番地 処理方法:連続流入ばっ気方式 汚泥処理:バキューム車により濃縮汚泥を搬出し、市のし尿処理施設で処分 |

(2)漁業集落環境整備事業
本市の漁業集落環境整備事業は、平成4年6月22日に農林水産大臣より事業承認を受け、平成5年度より本工事に着手、平成7年度に完了し、平成8年8月から供用開始しています。
|
事業名 |
漁業集落環境整備事業(農林水産省補助事業) |
|---|---|
|
事業年度 |
平成4年度〜平成7年度 |
|
総事業費 |
535,466千円 |
|
全体計画面積 |
10.5ヘクタール(阿多田島 8.3ヘクタール、猪子島 2.2ヘクタール) |
|
処理面積 |
10.5ヘクタール(平成29年3月31日現在) |
|
全体計画人口 |
471人 |
|
計画処理能力 |
日平均:128立方メートル |
|
施設概要 |
大竹市漁業集落排水処理施設 所在地:大竹市阿多田2番18 処理方法:接触ばっ気方式 汚泥処理:脱水ケーキをトラックで搬出処理 |

4.受益者負担金(分担金)
受益者負担金制度とは
下水道を整備するには多額の経費が必要です。一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数のものを整備する場合には、その建設費は公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を全市域から納められた税のみでまかなうとすれば利益を受けない人にも負担させることになり、住民の負担方法としては公正を欠くことになります。
したがって下水道施設の設置によって、利益を受ける人から受益の割合に応じ、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
大竹市では、この制度を取り入れ、建設費の財源に充てています。
受益者とは
下水道が整備されますと、公衆衛生が向上するなど公益をもたらすことはもちろんですが、下水道が整備される区域では土地の利用範囲が拡大 し、質的にも高度に利用し得るようになります。
受益者とは、公共下水道が布設される区域内に土地を持っているか、あるいはその土地に権利(地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借権)を持っている方のどちらかをいいます。
負担区とは
大竹市の下水道は昭和35年から着手しており、その当時の工事にかかった経費と現在の経費は同じ工事でも大きく異なります。したがって着工当時と現在の負担額が同じでは不公平が生じるので、市域を区切ってそのつど負担金の額を見直すものです。
参考
第1負担区(大竹・大竹の一部) 185円/平方メートル
第2負担区(大竹・大竹の一部) 262円/平方メートル
第3負担区(大竹・小方・木野の一部) 313円/平方メートル
第4負担区(大竹・小方・玖波第1の一部・玖波第2) 333円/平方メートル
単位負担金
1平方メートル当たりの負担金の出し方
(負担区の事業費の額×負担率)÷負担区の面積=1平方メートル当たりの負担金
負担率とは
国が示している負担率は1/3から1/5の範囲を適当としていますが、大竹市の場合は一番低い1/5を採用しています。
負担金はすべての土地にかかります。
河川、公園、公道などの公共用地は除かれますが、国、県、市の土地及び私有地のすべて(田、畑、宅地、雑種地など)に賦課されます。
負担金の徴収
年度当初の賦課対象区域を定めて公告します。区域内の土地所有者又は権利者の方には公告された年から5年(1カ年4期の20回)に分割して負担金 を納めていただくことになります。
負担金の一括納付報奨金
負担金は20回の分割で納付していただきますが、これを一括納付されますと、前納の回数に応じ、報奨金を交付します。
|
納期前に納付した納期に係る納付件数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
交付率 (%) |
2 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
|
納期前に納付した納期に係る納付件数 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
交付率 (%) |
16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
たとえば第3負担区の200平方メートル(約60坪)の土地に賦課された負担金を第1回目に全額納付されますと、
200平方メートル×313円=62,600円(負担金総額)
62,600円(負担金総額)-3,130円(第1期分)=59,470円(前納報奨金対象金額)
59,470円×30%=17,841円(前納報奨金)
62,600円-17,841円=44,759円(差引納付額)
になります。

5.水洗便所改造資金貸付金制度
公共下水道管布設工事が完了し公共下水道供給開始区域として告示がなされますと風呂、台所などの雑排水は3ケ月以内に、また水洗便所への改造は3年以内に行い、公共下水道管に接続していただくことになります。汲み取り便所を水洗便所に改造される方には、無利子で資金の貸付けを行っています。
貸付けを受けることができる人の要件
1.処理区域内における建築物の所有者又は使用者であること。
2.市税、下水道受益者負担金の滞納が無いこと。
3.市内在住の確実な連帯保証人があること。
貸付金額
汲み取り口1個の改造につき30万円以内。
貸付条件
1.貸付利息・・・無利子(供用開始後3年経過後は年8%)
2.償還方法・・・貸付けた月の翌月から40ケ月の元金均等償還
3.延滞利子・・・延滞償還金額につき年14.6%
資金の償還は、納入通知書により毎月末日までに次の取扱金融機関で行ってください。
四国銀行(大竹支店、市役所出張所、大竹支所派出所))
広島銀行
もみじ銀行
広島信用金庫
ひろしま農業協同組合
中国労働金庫(大竹支店)
広島県信用漁業協同組合連合会(広島西支店玖波代理店、広島西支店阿多田島代理店)
山口銀行
西京銀行
6.大竹市下水道指定工事店
詳細は下記のページをご覧ください。
7.おわりに
下水道工事は、人や自動車の交通事情を悪くしたり、一時的に付近の環境を悪化させたり、なにかとみなさまにご迷惑をおかけすることが多いと思われます。
こうしたことを最小限にしようと、下水道工事は最新の技術と工法を採用して懸命の努力をしています。お近くで下水道工事を行う場合には、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
なお、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
下水道に関するお問い合わせ
水洗便所改造貸付金、受益者負担金、下水道使用料に関すること
業務課 営業係
電話
(0827)59-2191
予算・決算その他庶務に関すること
業務課 総務係
電話
(0827)59-2193
下水道に関すること
工務課 下水道係
電話
(0827)59-2194
更新日:2023年09月01日