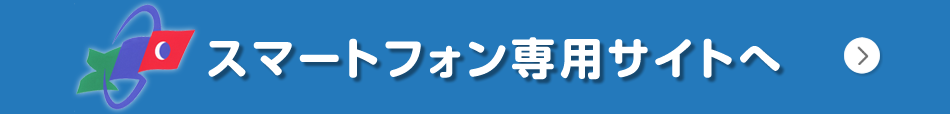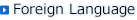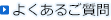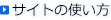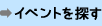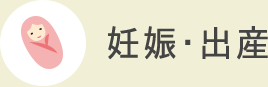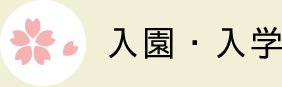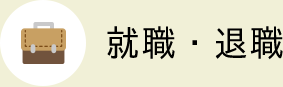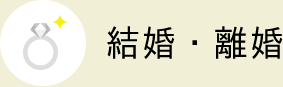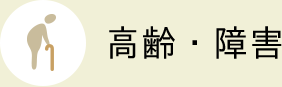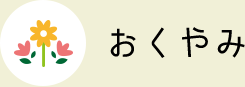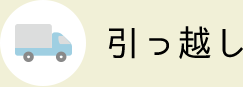成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的障害などにより、判断能力が十分でない方は、財産の管理や「契約を結ぶ」などの法律行為を行う際に、自分で判断することが難しい場合があります。 成年後見制度は、こうした自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所が選任した成年後見人(保佐人・補助人)などが、本人の身の回りに配慮しながら、財産の管理や介護サービスなどの契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。 年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。
法定後見制度の概要
判断能力が欠けている、または不十分な方で、契約などの法律行為が行えない場合に、本人の権利を守る制度です。 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を所管する家庭裁判所に申し立てをします。申し立てができる方は、本人、配偶者、4親等以内の親族などです。 法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれていて、本人の判断能力の程度で区分されます。
後見…ほとんど判断ができない方が対象
保佐…判断能力が著しく不十分な方が対象
補助…判断能力が不十分な方が対象 利用手続きの流れ
1.申し立て準備
戸籍謄本、医師の診断書、申し立てに必要な書類の作成 (印紙や切手の購入、戸籍謄本や診断書の費用として1万5千円程度必要)
2.家庭裁判所へ
大竹市の管轄は、広島家庭裁判所です。
申し立て3.審理の開始
裁判所調査官による調査(親族などへの照会、必要に応じて 本人と面談) 医師による鑑定が必要な場合もあります(鑑定料別途必要)
4.審判
申し立てから1~2か月後 成年後見人などの選任
5.審判確定
審判の告知から2週間後 成年後見などの業務の開始
注意 後見人などへの報酬は、本人の支払い能力に応じて、家庭裁判所が決定 します。
任意後見制度の概要
現在は判断能力があるが、将来の判断能力の低下に備え、「支援してもらいたいこと」、「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておき、自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。 手続は、判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)と、任意後見受任者を決め、公証役場で任意後見の内容について公正証書により契約します。公正証書の内容は東京法務局に登記されます。 本人の判断能力が不十分になったら、任意後見制度を利用するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申し立てをします。申し立てができる人は、本人・配偶者・4親等以内の親族・任意後見受任者などです。任意後見監督人が選任されると同時に、任意後見業務が開始されます。
利用手続きの流れ
1.本人と任意後見受任者が、どのようなサポートをするかなどを話し合います。
2.本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成し、契約を交わします。
注意:大竹市の近くの公証役場・・岩国公証人役場(岩国市今津町1-18-7)
3.本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。申し立ては、本人や4親等以内の親族、任意後見受任者が行うことができます。
4.審理の開始 裁判所調査官による調査や、医者による鑑定が必要な場合があります。
5.審判(申し立てから1~2か月後) 任意後見監督人が選任され、任意後見人の業務が開始されます。 注意:任意後見人には、本人との契約により決められた報酬、任意後見監督人には、本人の資力などに応じて家庭裁判所が報酬を決定します。
後見人などが行うことができる支援の内容
1. 介護・医療へのサポート 要介護認定の申請や介護サービスの利用契約、施設への入退所の手続き、医療機関の受診に関する手続きなどを本人に代わって行い、生活を見守ります。
2. 財産の管理 不動産の管理や預貯金の出入金を管理するなど、本人以外の人が勝手にお金を使わないようにします。
3. 契約の代理や取り消し 一人で行うことが難しい契約の締結や、本人にとって不利益な契約の取り消しなどを行います。
後見人が行うことができない支援
・直接的な介護や生活支援
・医療行為に関する同意(手術など生命・身体に危険を及ぼす可能性のある医療行為)
・結婚・離婚などの一身専属的な権利(相続や譲渡できないその個人だけの権利)
・施設契約時などの保証人や身元引受人など
| 認知症の父が、必要のない高価なものを買ってしまい困っています。 | 成年後見制度の開始後に行った、本人に不利益な契約を取り消しすることができ、本人の財産を守ることができます。 |
| 契約書の内容が理解できなくなり、介護や福祉サービスの契約を一人で行うことが心配です。 | 成年後見人などが、介護や福祉のサービスの契約を代理して行い、本人に必要な介護や福祉のサービスを受けられるよう支援します。 |
| 身寄りがいないので、認知症になった後の生活が不安です。 | 成年後見制度では、判断能力があるうちに、判断能力の低下に備えて、後見を行う人(任意後見人)を選び、やってほしい支援の内容を取り決めておくことができます。 |
市の取り組み
・法定後見制度市長申し立て 身寄りがない、身寄りの援助が期待できないなどの理由で、申し立てをする人がいない方の権利を守るために、市長が家庭裁判所に対して、成年後見制度の審判を申し立てることができます。
・成年後見制度利用支援事業 市長申し立てを行った方で、その申し立て費用及び後見人報酬を支払うことが困難な場合は、助成を行っています。
・相談対応 成年後見制度についての相談は、つぎのところでお受けします。お気軽にご相談ください。
・健康福祉部地域介護課 地域支援係(市役所内) 電話 28-6226
・大竹市地域包括支援センター(大竹市社会福祉協議会内) 電話 53-1165
・大竹市認知症対応・玖波地区地域包括支援センター(メープルヒル病院内)
電話 57-7461
更新日:2024年05月15日