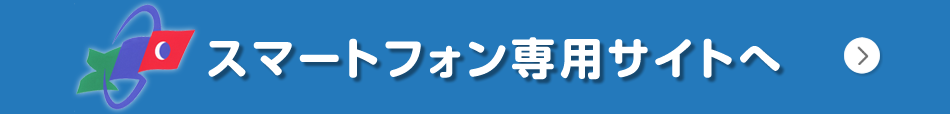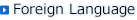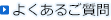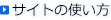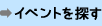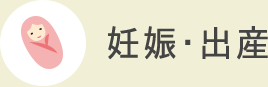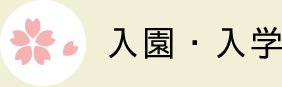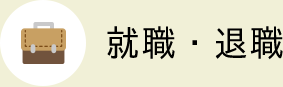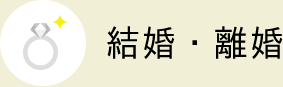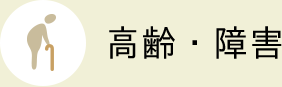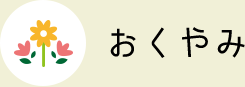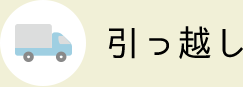高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき
1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が次表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
- 合算する期間(計算期間)
毎年8月1日から翌年7月31日まで - 合算できる範囲
同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者に係る自己負担額(ただし、高額療養費等の支給該当額を除きます)
| 区分 | 自己負担限度額(年額・世帯単位) 医療保険+介護保険 |
|
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 現役並み所得者3(注意1) | 212万円 |
| 現役並み所得者2(注意1) | 141万円 | |
| 現役並み所得者1(注意1) | 67万円 | |
| 一般(注意2) | 56万円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2(注意3) | 31万円 |
| 低所得者1(注意3) | 19万円 | |
(注意1)負担区分が3割の方です。現役並み所得者の区分については、現役並み所得1は課税所得が145万円以上380万円未満、現役並み所得2は課税所得が380万円以上690万円未満、現役並み所得3は課税所得が690万円以上となります。
(注意2)一般とは、現役並み所得者、低所得者以外の方
(注意3)負担区分が1割で、区分については低所得者1は同一世帯全員が市町村民税非課税で世帯の各種所得合計額が0円の方(公的年金控除額806,700円で計算)で、低所得者2は同一世帯全員が市町村民税非課税世帯で低所得者1に該当しない方です。
- 負担限度額の区分は、毎年7月31日現在の医療保険での区分を適用します。
- 算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
- 医療保険または介護保険のどちらかの自己負担限度額の合算額が0円の場合や、自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
申請手続きについて
- 計算期間中に医療保険と介護保険の両方で異動のない方
支給の対象となる方には、1月頃に広域連合から申請案内が送付されます。申請案内に同封されている申請書に必要事項をご記入のうえ、国保年金係に申請してください。一度申請した方でも、毎年の申請が必要です。
- 計算期間中にいずれかの保険で異動のあった方
申請案内が送付できない場合がありますので、該当されると思われる方はご相談ください。
申請に必要なもの
- 支給申請書(申請案内に同封のもの)
- マイナ保険証または資格確認書(マイナ保険証の場合は、「マイナポータルの資格情報画面の写し」を提出してください。)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳など)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- いずれかの保険で異動のあった場合、以前の保険の自己負担額証明書
(注意)被保険者が亡くなっている場合は、相続申立書や相続関係確認書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
更新日:2024年12月01日