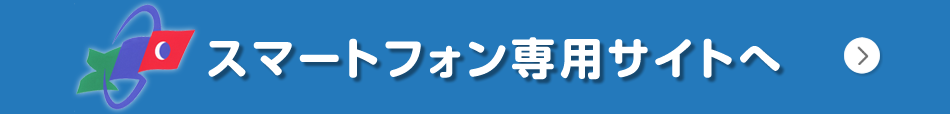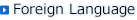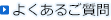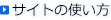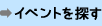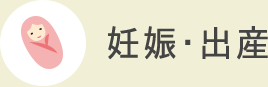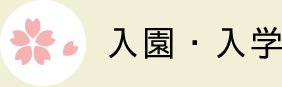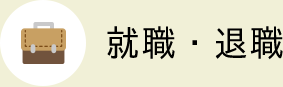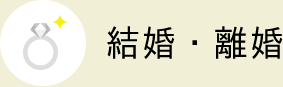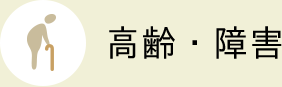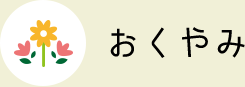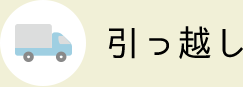特別児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
精神または身体に障害があり、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童の福祉の増進のため、その児童を監護している父母(主としてその児童の生計を維持している方)、または父母にかわって児童を養育している方に手当を支給します。
支給を受けるための要件
「障害程度基準表」に掲げる程度の障害の状態にある児童を監護している父、母または養育者が支給の対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
- 手当を受けようとする方(父、母または養育者)または児童が国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合(その全額が支給停止されている場合を除く。)
| 1級 |
|
|---|---|
| 2級 |
|
支給金額
1級障害児童1人につき:月額 56,800円
2級障害児童1人につき:月額 37,830円
(令和7年4月~)
所得による制限
前年の所得(請求月が1〜6月の場合は前々年)が次の限度額以上の場合は支給されません。
| 税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数 | 受給者本人 | 受給者の配偶者、扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
- 受給者となるのは父・母のいずれか所得の高い方です。
- 扶養義務者…手当の受給者と生計と同じくする受給者の父母、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹など
支給日
4月・8月・11月の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に、支給する月の前月分までの手当を振り込みます。(特別児童扶養手当は、請求日の属する月の翌月分から支給されます。)
手当の支給は広島県が行います。
請求の手続き
- 初めて手当を請求する方
- 他市町村で手当を受給中で、大竹市に転入してきた方
- 現在手当を受けている方(支給停止の方を含む)
・更新の手続き(所得状況届)
・有期再認定の手続き
・変更の手続き(児童数の増減、住所・氏名・金融機関の変更など)
初めて手当を請求する方
請求する期間
児童に障害があることが判明した日以降
請求する場所
福祉課障害福祉係(郵送不可)
障害の審査は、国が定める障害程度認定基準に基づいて広島県が行います。
請求ができる方
児童を監護・養育している父、母、養育者
持参するもの
(1)戸籍謄本(1か月以内に交付されたもの)
- 父と子または母と子のもの
- 養育者の場合は、手当の対象となる児童の父母の戸籍
(2)診断書(2か月以内に診断されたもの)
障害の種類によって用紙が異なります。(用紙は福祉課にもあります。)
手帳の等級などにより診断書が省略できる場合があります。
(下記「診断書が省略できる場合」をご覧ください。)
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
(4)請求者名義の振込口座を確認できるもの
(手当の支給が決定した場合に、手当の振込先となる金融機関のもの)の写し
(5)請求者、配偶者および扶養義務者、対象児童全員分の個人番号が分かる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
(6)運転免許証など顔写真付きの身分証明書
(個人番号の本人確認用として必要です。顔写真がない身分証明書の場合は2種類以上必要です。)
市役所で記入していただくもの
特別児童扶養手当認定請求書
注意事項
- 請求者が子どもと別居している場合は、別居している子どものいる世帯全員の住民票を添えて「別居監護の申立て」を行ってください。(用紙は福祉課にあります。)
民生委員・児童委員、寄宿舎の長、学校長などの証明が必要となります。 - 養育者の場合は、「養育申立て」を行ってください。(用紙は福祉課にあります。)
民生委員・児童委員の証明が必要となります。 - 児童を監護する父・母のいずれもその児童の生計を維持していない(所得なし)場合は、「介護申立て」を行ってください。(用紙は福祉課にあります。)
- 手当を受けられるのは、対象となる児童の20歳の誕生日の前日までです。
- 特別児童扶養手当は、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
(請求書の記載事項や請求に必要な書類に不備がないことが確認でき、受付が完了した日が請求日となります。) - 請求がない場合は手当を受けることができません。また、書類などに不備があり、正当な理由なく、市が指定する期限までに提出などがない場合は、請求を却下する場合があります。
診断書が省略できる場合
身体障害者手帳をお持ちの方
「身体障害者障害程度等級表(下記PDFファイルをご覧ください)」のうち、診断書が省略できる障害・等級に該当する場合
- 内部障害の場合は必ず診断書が必要です。
- 複数の障害がある場合は、総合等級ではなく個々の障害・等級で判断します。
身体障害者障害程度等級表 (PDFファイル: 382.6KB)
療育手帳をお持ちの方
障害の程度が「A(「特別児童扶養手当診断書省略」の印付)」または「マルA」と記載されている場合
他市町村で手当を受給中で、大竹市に転入してきた方
他市町村から転入された方は、「住所変更届」を提出してください。(用紙は福祉課にあります。)
受給者本人、児童、配偶者および扶養義務者の個人番号の記入が必要となりますので、個人番号カードまたは通知カードを提示してください。(受給者本人以外の個人番号は、受給者本人が代わりに記載することで、個人番号カードなどの提示は不要です。 また、本人確認用として運転免許証など顔写真付きの身分証明書を提示してください。(顔写真がない身分証明書の場合は2種類以上必要です。)
転入処理には一定の時間がかかります。手当の支給日が近い場合、支給日にお支払いできない場合がありますのでご了承ください。(支給日に間に合わない場合、支給日の属する月の翌月以降となります。)
現在手当を受けている方(支給停止の方を含む)
更新の手続き(所得状況届)
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8〜9月に「所得状況届」を提出していただく必要があります。(対象となる方には8月上旬に市から書類を送ります。)
この届は、最新の所得の状況などを確認し、引き続き手当を受給する要件があるかどうかを審査するものです。(手当が全部停止となっている方も提出が必要です。)
| 提出する期間 | 8月12日〜9月11日 |
|---|---|
| 提出する場所 | 福祉課障害福祉係(郵送可) |
| 持参するもの |
(1)特別児童扶養手当所得状況届 (2)受給者、配偶者、扶養義務者および対象児童全員分の個人番号が分かる書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど) |
| 注意事項 |
|
有期再認定の手続き
特別児童扶養手当の認定を適正に行うため、障害の程度によって、必要に応じて認定期間が定められます。現在手当の支給を受けている方で、認定期間満了後、引き続き手当の支給を受けるためには、更新手続き(有期再認定)が必要となります。
提出する期間
認定期間の満了日の属する月の末日までに
提出する場所
福祉課障害福祉係(郵送可)
持参するもの
(1)特別児童扶養手当有期再認定請求書
対象となる方には認定期間満了日の1〜2ヶ月前に用紙を郵送します。
(2)診断書(2か月以内に診断されたもの)
障害の種類によって用紙が異なります。(用紙は福祉課にもあります。)
手帳の等級などにより診断書が省略できる場合があります。
(上記「診断書が省略できる場合」をご覧ください。)
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
注意事項
- 障害の程度が変わったとき(手帳の等級が変わった時など)は、別の手続きが必要となる場合があります。
- 正当な理由がなく、認定期間が満了する月末までに提出がない場合は、認定期間が満了する月の翌月分から手当が支給されなくなります。
- 手当の対象となる児童が2人以上いる場合、認定期間が更新されていない児童がいると他の児童分の手当も支給されなくなりますのでご注意ください。
変更の手続き(児童数の増減、住所・氏名・金融機関の変更など)
次のような場合には市役所への届出が必要です。(用紙は福祉課にあります。)
届出の際は必ず証書をお持ちください。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
| 受給資格に該当しなくなったとき | 次のようなときは受給資格喪失の届出が必要です。
|
|---|---|
| 手当の対象となる児童が増えたとき | 手当額の改定(増額)請求ができますので、必要な書類とともに請求を行ってください。(必要な書類は、初めて手当を請求する際に必要な書類と同じです。) |
| 手当の対象となる児童が減ったとき | 手当の対象となる児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなった場合や監護しなくなったときなどは、手当額が変更となりますので、届出を行ってください。 2人以上の対象児童のうち20歳の誕生日を迎えた児童がいる場合、届出を行わないと他の児童分の手当も支給されなくなりますのでご注意ください 。 |
| 障害の程度が中度から重度になったとき | 手当額の改定(増額)請求ができますので、障害程度が重度になったことが分かるもの(診断書・身体障害者手帳または療育手帳の写し)とともに請求を行ってください。 |
| 障害の程度が重度から中度になったとき | 手当額が変更となりますので、障害程度が分かるもの(診断書・身体障害者手帳または療育手帳の写し)とともに請求を行ってください。 |
| 対象児童が転居したが、引き続きその対象児童を監護するとき | 手当の対象となる児童が他の住所地に転出したが、引き続きその児童を監護するときは、「別居監護申立て」を行ってください。(その児童の居住する地区の民生委員・児童委員などの証明が必要です。) |
| 市外へ転出するとき | 住所変更の届出を行ってください。また、転出先の市町村の特別児童扶養手当担当課でも住所変更の届出が必要です。 |
| 住所を変更したとき | 住所変更の届出を行ってください。 |
| 氏名を変更したとき | 氏名変更の届出を行ってください。 手当の対象となる児童の氏名を変更したときも同様です。(新しい戸籍謄本の提出が必要です。) |
| 手当の支払金融機関や口座名義を変更したとき | 支払金融機関変更の届出を行ってください。(預金通帳の写しを添付してください。) |
更新日:2025年04月01日